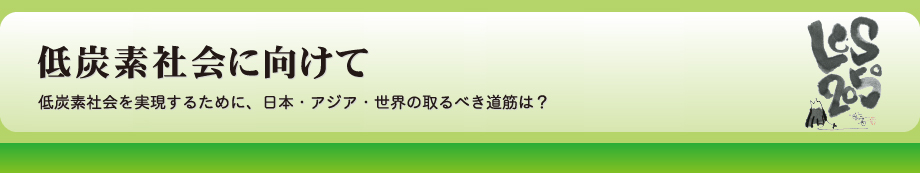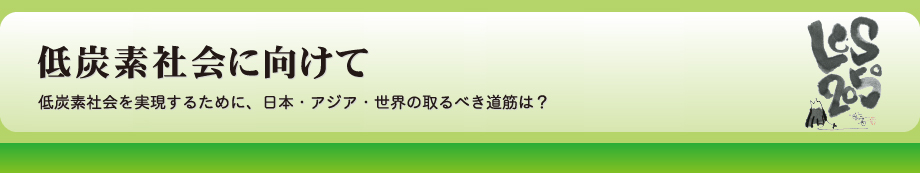| |
本セミナーの目的 |
| |
消費が創る低炭素社会 |
| |
(独)国立環境研究所 地球環境研究センター 主任研究員 藤野 純一 |
| |
|
| |
G8ハイリゲンンダムサミットで提唱された「50 by 50」(2050年に世界の温室効果ガスは排出量を現状から50%削減する)を実現するには、
日本でも大幅な削減が求められる。政府は炭素税や排出量取引のルール作り、
カーボンラベリングなどに必要な情報の基準作り、産業はGHG排出とデカップリングしたサービスの創造、
雇用の確保、そして市民は低炭素社会・循環型社会に適う消費活動を行い、
政府や産業に関して適切にモノを言うことが求められる。
政府・産業・市民が一体となったTrustに基づく低炭素社会・循環型社会作りはできないか? |
| |
発表資料はこちら → ppt資料
 (427KB) (427KB) |
| |
|
| |
基調講演 1 |
| |
ユニー(株)の「小売業の地球温暖化防止への役割・・・お客様と一緒に進める環境保全活動」 |
| |
ユニー株式会社 環境社会貢献部 部長 百瀬 則子 |
| |
|
| |
これからの低炭素社会を構築していくには、一般市民(生活者)の生活、特に消費生活を変えなくては実現できません。
一般市民(生活者)=消費者と捉えると、小売業が果たす役割は大きいと思います。
消費者が商品やサービスを購入したり、ライフスタイルを選択することにより、低炭素社会に近づく・・・
そんな役割を小売業は果たすべきだと考えています。
まず最初は、現在販売している商品やサービスの[環境に及ぼす影響]を消費者に情報提供し、
消費者にそれらにより「環境に配慮した選択」を実践してもらうことだと思います。
是非、研究者の皆様と協働で取組んでいきたいのです。研究者の作られたシナリオのアクターは、
消費者であることをお忘れなく! |
| |
発表資料はこちら
ユニー環境レポート2007
http://www.uny.co.jp/corporate/torikumi/eco/management/report.html
ユニー㈱ 環境配慮に対する方向性の考え方
 (2.38MB) (2.38MB)
グループインタビューの分析
 (4.91MB) (4.91MB) |
| |
|
| |
話題提供 |
| |
消費活動に伴う間接資源消費・環境負荷の分析と応用 |
| |
(独)国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター長 森口 祐一 |
| |
|
| |
消費活動の背後にある間接的なエネルギー消費・CO2排出については、1970年代のエネルギー・アナリシスをはじめ、
多くの分析事例がある。こうした間接的な資源消費・環境負荷の数量化は、バーチャルウオーター、
エコロジカル・フットプリント、エコロジカル・リュックサックなどと概念的には共通しており、
カーボンフットプリントもその一つである。より包括的な分析であるライフサイクルアセスメント(LCA)や、
タイプ3のエコラベルなども含め、関連する調査研究とその応用について概観する。 |
| |
|
| |
基調講演 2 |
| |
産業連関分析によるCO2排出原単位のカーボンラベルへの利用可能性 |
| |
(独)国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター 研究員 南斎 規介 |
| |
|
| |
カーボンラベルの表記には,商品のカーボンフットプリントの計算をしなくてはならない。
商品の生産者ではなく,それを販売する小売店が自ら商品のカーボンフットプリントを計算するには,多大な労力を要する。
また,取り扱う商品の種類も数も多い。しかし,産業連関分析により得られるCO2排出原単位を利用することで,
その労力を軽減できる可能性がある。CO2排出原単位の読み方やそれから得られる情報について紹介する。 |
| |
発表資料はこちら → ppt資料
 (1.49MB) (1.49MB) |
| |
|
| |
午前の部 議論の内容メモ
 (28KB) (28KB) |